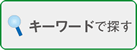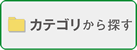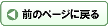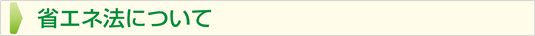
|
|
[1970年代]2回のオイルショックを受け、省エネ対策 | |
|
しかし、エネルギー消費量は年々増加の一途を辿った。 |
||
| [1979年施行]エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) | ||
|
エネルギーを効率的に使用するため、工場や建築物、機器、運輸、家庭などで省エネを進めるための措置を定めた法律。指定された工場ではエネルギー管理者の選任や定期的な報告、また、機器のエネルギー消費効率に省エネ基準を設定して省エネ化を促すといった措置を取ることが求められる。 |
||
| [1997年]気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)・・・京都議定書 | ||
|
二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの削減目標が定められ、日本も2008年から2012年の間に平均値で6%削減することを約束 |
||
| [1998年改正] | ||
|
自動車や家電などの機器のエネルギー消費効率を向上するため、「トップランナー方式」が導入された。 |
||
| [2005年改正] | ||
|
エネルギー消費の伸びが著しい民生・業務部門における省エネルギー対策の強化などを目的に改正 1) 工場・事業場に関するエネルギー管理についての規制の一本化、 原油などエネルギー価格の高騰や地球温暖化対策の今まで以上の推進が強く求められており、エネルギー消費量が増加している業務・家庭部門でも省エネを進める必要がある。こうした背景のもと・・・・ |
||
| [2008年改正] | ||
| 大規模な工場・オフィスに対して工場単位で義務づけてきたエネルギー管理義務を事業者単位で行うこととし、オフィスやコンビニエンスストアなどにも拡大。工場や事務所などで年度内に1500kl以上のエネルギーを使う事業者には、国への報告義務がある。 また、家庭・業務部門における省エネ対策が強化されたほか、住宅と建築物に関する省エネ対策が強化、拡充された。住宅を建築、販売する事業者による住宅の省エネ性能向上を促す措置が導入され、事業者の努力義務に、一般消費者への省エネ性能の表示による情報提供が追加 | ||